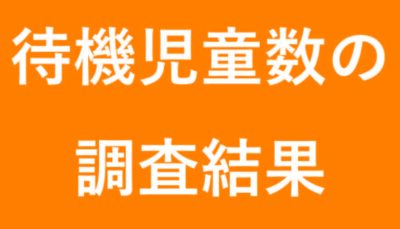待機児童数の調査結果について
待機児童数の調査結果について
2024年6月19日
日本共産党東京都議会議員団
日本共産党都議団は、東京都の区市町村における今年4月1日時点の待機児童数の調査を行いました。その結果についてお知らせします。
主な結果
- 調査期間:5月1日~5月21日
- 国定義の待機児童数は、回答のあった18区24市5町8村で、264人でした。
- 「隠れ待機児童」(区市町村に認可保育園等(※)の利用を申し込んで入れなかったが、国定義の待機児童数に含まれない子ども)の理由別の人数についても調査をしました。人数が分かったのは17区24市5町8村で11,965人でした。
- そのため、実質的な待機児童数(=区市町村に認可保育園等(※)の利用を申し込んで入れなかった子どもの人数。国定義の待機児童数と「隠れ待機児童」の人数を合わせた人数)は、18区24市5町8村(うち1区は国定義の人数のみ)で12,229人でした。
- 区市町村別の結果は別表のとおりです。
※認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育など)。
補足:待機児童の定義について
- 以前は、国が定める待機児童の定義は、区市町村に認可保育園の利用を申し込んで入れなかった子どもというシンプルなものでした。
- しかし、2002年に待機児童数を小さく見せるために定義が変更され、認可保育園に入れなくても、認証保育所のように地方自治体が独自に補助している保育施設を利用している場合や、育児休業を延長した場合、求職活動を休止している場合などは待機児童とみなされなくなりました。
- そのため、自治体が公表している待機児童数は少ないのに、実際には認可保育園に入るのが困難だという事態が各地で生じるなど、国の定義する待機児童数は実態を正しく反映しないものとなりました。待機児童数から除外された子どもは「隠れ待機児童」と呼ばれています。
- その後は、国による待機児童の定義は、ある程度の変更はありましたが、大きな変更はなく、保育園に入れなかった子どもでも様々な理由で待機児童数から除外されている状況は続いています。
- 小池知事が「待機児童はほぼ解消」と述べているのは、国の定義による待機児童数を根拠にしたものです。
- 本調査では、実態を正しく反映するため、以前と同様、区市町村に認可保育園等(※)の利用を申し込んで入れなかった子どもの人数を実質的な待機児童数としました。
※現在は2002年当時と異なり、認可保育園とともに認定こども園や地域型保育事業(小規模保育など)も区市町村に利用を申し込む仕組みとなっているため、これらを含めて「認可保育園等」としています。
以上
6月20日追記
昨年の人数との比較は以下の通りです(比較可能な自治体での比較を行いました)。