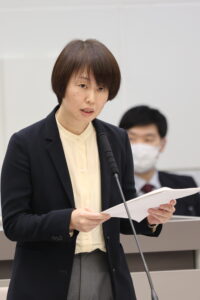予算特別委員会 福手ゆう子都議(文京区選出)の一般総括質疑
★動画(都議会ホームページです。)
★議事録速報版より
1.若者や生活困窮者への住まいの支援について
2.子どもの権利と安全・安心に学べる学校環境について
3.補助犬の医療費補助について
4.特別養護老人ホームにおける水道料金負担について
○福手委員 よろしくお願いいたします。住まいの問題について質問をしていきます。
まず、若者のことについてお聞きしていきたいと思います。
都営住宅の入居の対象ではない、住まいに困窮する若者などに対して、住まいの支援が必要と考えますか。伺います。
○小笠原住宅政策本部長 都は今年度から、就職氷河期世代などの低所得の若年、中年単身者が、住まいの安定を図りながら就労自立していくモデルの構築を目的に、区市、社会福祉法人等、関係局と連携いたしまして、都営住宅の空き住戸を試行的に期限付で提供することに取り組んでおります。
○福手委員 就職氷河期世代等の低所得の人たちに期限付で都営住宅の提供をモデル実施されているとのことですが、それ自体は大事な取組ですが、それだけでは間に合わない、本当に深刻な事態が若者たちの間に広がっています。
今日泊まるところがないという状況になった若者に、相談は翌日にして、申し込んだその日に必ず泊まるところを提供するという支援が都内近郊で行われています。
この支援団体の方にお話を伺いました。
昨年は、延べ千件の相談を受けてきたそうです。支援を求める方がどのような状況にあるのかを伺いました。
十代は、家庭環境が悪く、家を飛び出した人が多く、二十代は、ネットカフェや個室ビデオ店で過ごし、隙間バイトで、その日のお金を稼いでいるとのことでした。
隙間バイトは二十から五十代の八割から九割が登録をしていて、アプリで仕事を探し、すぐ仕事に入ることができます。そのため、夜まで仕事を探せますが、逆にいえば、その日仕事に入れるのか、入れないのかが夜まで確定しないという状況があります。
それで結局、仕事に入れなかったり、例えば夜の七時にその日仕事がないことが確定し、それから、その日泊まる場所をどうすればよいかと困ることになる、以前とは全くスピードが違うと話されていました。このような不安定な生活をしている人たちが支援につながっているとのことでした。
都は、二〇一六年度にネットカフェ調査をやっていますが、当時は隙間バイトはありませんでした。当時とは大きく働き方が変わっています。その実態を改めて調査することが必要です。都として、住宅喪失不安定就労者等の実態調査が必要ではありませんか。
○山口福祉局長 都は、住居喪失不安定就労者等を支援するTOKYOチャレンジネットや、ホームレスの就労自立を支援する自立支援センターなどを通じまして、住居を失うおそれのある方やネットカフェの利用者などの状況の把握を行っております。
○福手委員 把握しているといいますが、それでは不十分だから、二〇一六年度調査をしたんではないですか。それから八年もたって、状況も変わっているのに、調査をしていなくてよいということにはなりません。調査をしなければ、先ほどのような今の若者のリアルな働き方や住まいの実態を東京都がきちんとつかむことはできないと思います。改めて実態調査の実施を要望しておきます。
TOKYOチャレンジネットは、ネットカフェなどに寝泊まりし、不安定な就労をしている人に対して、一時的な住まいを提供する制度です。大事な役割を持っていますが、この制度を一度利用した方は二回目の利用ができません。
支援団体の方にお聞きしますと、今の若者はどうしてここまで頑張るのかと思うくらい頑張る人が多いといいます。みんな毎日隙間バイトで今日の仕事を見つけて、その日の生活費を稼いで、また次の日も同様に仕事を探し続けているんです。
二十代で若ければ、まだ体力があるかもしれませんが、それでもこうした生活は半年ともたない人がほとんどだといいます。そのような方が支援につながったときに、チャレンジネットを使えるとよいと思うことがありますが、既にチャレンジネットを使ったことがあると使えません。それこそ、チャレンジネットができた頃に使ったので、もう使えない方もいるとのことです。
もう一回チャレンジネットが使えたら生活を立て直す支えときっかけになると思うんです。TOKYOチャレンジネットの一時住宅制度を一度使ったことがある人でも、条件をつけて、二回目も使えるように拡充することを求めます。
また、自立支援は、就労の自立だけではなく、社会生活や日常生活の自立支援も同じく重要です。TOKYOチャレンジネットの就労条件を緩和することも含めて、制度の見直しを求めておきたいと思います。
生活を立て直したいと思っても、不安定就労者が賃貸契約を結ぶにはハードルがあります。一つは、お金の問題です。
せっかく家賃が安い部屋を探しても、敷金、礼金も払わなければならない物件だと借りられません。都として、敷金、礼金など、部分的な補助制度をつくることで、住まいの支援ができるのではないでしょうか。
○小笠原住宅政策本部長 都は、低額所得者などの住宅確保要配慮者の居住の安定確保のため、都営住宅や民間賃貸住宅を活用し、重層的な住宅セーフティーネット機能の強化を図っております。
民間賃貸住宅を活用した東京ささエール住宅の専用住宅におきましては、区市と連携をして、家賃低廉化補助を実施することにより、入居者の負担軽減も図っております。
○福手委員 大家さんに対して補助を出す家賃低廉化補助制度の答弁がありましたが、都内では、制度を持つ自治体の数も、実績も少なく、実際には家賃が高くて借りられない物件が多いという声があり、住まいに困っている人が使える制度にはなっていないのが実態です。
さらに、賃貸契約する際のハードルとして、与信、つまり、支払い能力などの審査が通らないという問題があります。審査を行う背景には、家賃滞納されたら困るという問題があります。やはり所得に応じた家賃になるような家賃補助や敷金、礼金の補助が必要です。改めて、補助制度の新設を求めておきます。
都営住宅の活用ももっとできることがあります。
私は、尼崎市のREHUL事業の取組を視察してきました。尼崎市では、市営住宅の建て替えに当たって、入居募集を停止していることで空き家が増加し、自治会活動に支障が出ていました。その課題を解決するため、市が空き家を目的外使用によって、各種支援団体や地域活動団体の活動の場として、低い料金で提供しています。そうすることで、住宅の確保が困難な方の支援も行うことができます。
REHUL事業は、建て替え対象で募集停止している住宅の空き家の活用なので、期間限定の貸出しで、市民から不公平という声は上がりません。修繕なしで貸すため、市の予算もかかりません。
支援団体が制度を利用したい場合、市営住宅の担当職員が、状態が良好な住宅の中から、希望に合わせた立地や間取りの住宅を選び、さらに内覧にも立ち会います。そうして団体が、目的外使用許可を受けた住宅に相談者が入居したいと決めたら、すぐ鍵を渡すこともできるので、本当に住まいを探している人に寄り添った対応ができています。
私はここが本当に重要なポイントだと思って聞いていました。住まいに困っている人にいかに迅速に住まいを提供できるか、これが命を救うことにもつながるからです。
目的外使用の住宅を使って、民間支援団体が支援する場を提供することは、都の間接的にできる住まいの支援になると思います。見解を伺います。
○小笠原住宅政策本部長 都はこれまでも、公営住宅法及び東京都営住宅条例に基づき、都営住宅の住戸につきまして、適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、社会福祉法人等に目的外使用許可を行っております。
具体的には、知的障害者グループホームや、TOKYOチャレンジネットにおける就労を目指す離職者などを対象とする一時利用住宅として提供しております。
○福手委員 都としても既に目的外使用で一時利用住宅を提供しています。大事な取組であり、さらに広く活用していくことが重要だと思います。さらに、REHUL事業のように、建て替えで募集停止の住戸を活用すれば、もっと取組を充実させることができると思います。
そこでお聞きしますが、現在、建て替え対象で募集を停止している住戸、幾つありますか。
○小笠原住宅政策本部長 都営住宅を良質なストックとして維持更新していくため、地域の特性や老朽化の度合いなどを勘案しながら、計画的に建て替えを行っております。
建て替えを円滑に進めるため、閉鎖する予定の住棟につきましては入居者の募集を停止しております。
令和五年度末現在、募集を停止している住戸数は約八千五百戸でございます。
○福手委員 八千五百戸あるということでした。昨年の予特の私の質問で、東京都は、公募を停止した住戸は老朽化が進み、建て替える予定のものなので使用しないと答弁していますが、尼崎市のように、移転事業の開始までの期間限定でも使用できると判断すれば、様々な支援を提供できると思うんです。
尼崎市は現在、六百八十戸の目的外使用の承認を受けていて、これは全国で一番多い戸数で、来年度さらに追加するといっていました。国交省もこれを認めています。
なぜここまで増やすかといいますと、それだけ住まいに困窮している人が求めていることを知っているからなんです。建て替えまでの限られた期間だけど、だけど使おうと。行政として何かできることがあるかと考え、足を踏み出した結果がこういう状況になっているんです。こうした寄り添った対応が東京都にも求められます。
また、住まいの支援は、入居できればそれで終わりではなく、入居後も定期的な見守りや支援を行うことが必要な場合があります。民間賃貸住宅において、そのコーディネーターの役割を果たせるよう、支援団体が関われるような仕組みを入れることは、住まいの支援として有効と考えますが、いかがですか。
○小笠原住宅政策本部長 都は、いわゆる住宅セーフティーネット法に基づいて、特定非営利活動法人や一般社団法人、一般財団法人、その他の営利を目的としない法人または住宅確保要配慮者の居住の支援を目的とする会社であって、支援業務の具体的な内容やその実施方法、実施体制などが適切であることや、支援業務を的確に実施できる健全な財務状況であることなど、法令で定める基準に適合するものを居住支援法人として指定をしております。令和七年二月末現在、五十二の法人を指定しております。
居住支援法人は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に係る支援や、入居後の見守りなどの生活支援を行っております。
○福手委員 私も幾つかの居住支援法人の方のお話を伺っていますが、皆さんそれぞれ住まいの課題をどう解決していくか、真剣に考えて取り組まれています。ここでも尼崎市の取組は参考になると思っています。
REHUL事業には、若年女性、難民の外国人、DV被害者、ホームレスの人たちなどなど、本当に様々な人を支援する団体が現在二十一参加していて、生活協同組合コープこうべが窓口になって、ネットワークに参加する支援団体に空き家を貸し出しています。
それぞれ得意とする支援をしている団体がつながって、幅広い支援を提供することができています。そのため、福祉がうまく支援できていなかったケースでも、REHUL事業で受け入れることができています。外務省から難民の外国人の受入れの依頼もあったそうです。
若い女性をREHUL事業の自立支援型シェアハウスで受け入れている団体で、一年前後の支援で生活スキルを身につけ、その後、支援のステージが変わった際に、同じ団体のつくったステップハウスにつなげ、継続した支援ができている取組もお聞きしました。
私は、この尼崎市の取組を参考に、都でもできることがあると思いました。都内では、独自でシェルター事業を行い、居住支援や生活支援で実績を持っている民間支援団体があります。こうした団体の実践に学び、参考にし、必要な連携をすることで、より多くの困っている人を支援することができると思うんです。ぜひ検討していただきたいと思います。
次に、生活困窮者自立支援制度についてです。
ホームレス状態にある人を支援することは、住まいの支援の中で特に重要な課題です。住まいは生活の土台だからです。
そこで伺いますが、生活困窮者自立支援制度には、一時生活支援事業という、ホームレス緊急一時宿泊事業、いわゆるシェルター事業があります。生活困窮者自立支援制度の一時生活支援事業の対象者、どうなっているのか伺います。
○山口福祉局長 生活困窮者自立支援制度における生活困窮者一時生活支援事業には、宿泊場所の供与などを行う事業と、訪問による見守りや生活支援などを行う事業がございます。
このうち、宿泊場所の供与などの対象者は、生活困窮者自立支援法及び同法施行規則で定められておりまして、一定の住居を持たない生活困窮者で、本人及び同一世帯に属する者の収入及び金融資産の合計額が一定額以下の者または緊急性などを勘案し当該事業による支援が必要と認める者とされております。
○福手委員 私は昨年の予特の場で、就労が認められず、社会保障制度も適用されないため、収入が全くなく、住むところも不安定で、貧困に苦しむ仮放免者への支援を求めて質問をしました。外国人のホームレスは増加しており、妊婦でさえも何の支援もなく、路上生活をする事例が都内でも複数あり、命や健康に関わる非常に深刻で緊急性が高い状況でありながら、民間支援団体による支援があるだけで、事態は変わっていません。
先ほど一時生活支援事業の対象について答弁されました。厚労省に問い合わせたところ、一時生活支援事業を含む生活困窮者自立支援制度では、在留資格に関する要件は法令上設けておらず、一時生活支援事業の支援対象者についても在留資格の有無は問われないと答えていますが、東京都の認識も同様か確認しますが、いかがですか。
○山口福祉局長 生活困窮者一時生活支援事業の対象者は、生活困窮者自立支援法及び同法施行規則において、一定の住居を持たない等の生活困窮者と定められておりますが、在留資格に関する要件は定められておりません。
○福手委員 在留資格は要件に定められていないということでした。つまり、在留資格は問われていないと、東京都も同様の認識であることを確認しました。
なぜ在留資格の有無を問わず、全ての人を対象としているか。生活困窮者自立支援制度は、聞いたところ、厚労省の担当者は、制度のはざまに陥る人を包括的に支援するものなので、制度創設に当たり、こういう人は対象外というようにはしていなかったと話されていました。
しかし、実態としては、民間の支援団体などからは、自治体の自立支援の窓口では、在留資格がない人は対象外として対応されていないケースが出ていると聞いています。東京都もそういう声を聞いているのではないでしょうか。
法律上は利用できるのに、自治体で排除することはあってはならないと思います。改めて法の趣旨や対象を区市町村と共有し、運用が速やかに改善されるよう取り組むことを強く求めます。
尼崎市へ視察した際に、コンゴから小さな子供二人を連れて日本に逃れ、しばらく路上生活をした後、REHUL事業につながった家族にお会いしました。REHUL事業で市営住宅を借りて生活をされていました。
市営住宅に入れても、この家族に降りかかる問題はまだたくさん残っています。ただ、お子さんは近くの小学校に通い、両親は地域の日本語教室で日本語を習い、REHUL事業に関わる市の職員や団体の皆さんがこの家族を支え、孤独にさせないで関わり続けている、そういう関係ができていることが分かりました。こうやって命を守ることができるのだと希望を感じました。
東京都でもできるはずです。踏み出してほしいと心からお願いをしたいと思います。
高齢者、外国人、ひとり親、非正規単身者、ホームレス状態にある人、LGBTQプラスなど、住宅弱者がいる中で、住宅は自己責任という考えが日本には根深くあります。この住まいの貧困は、住宅市場や住宅政策が標準世帯以外を排除してきた、その結果にあります。
東京は全国で一番家賃が高い都市です。そして、多様な人が集まる都市です。住宅問題があたかも外国籍の人、特にアジアの外国人が東京に住むことで、日本人が東京で住み続けられないような議論がありますが、そうではありません。むしろ、誰もが安心できる住まいを確保でき、どこに住むかはその人が決める、そのことがちゃんと権利として当たり前に保障される社会をつくることが必要です。都がその先頭に立つことを強く求めて、次のテーマに移ります。
2.子どもの権利と安全・安心に学べる学校環境について
○福手委員 まず初めに、東京都の基本姿勢を確認していきます。
東京都こども基本条例は、子供が健やかに育っていく環境の整備を求めていますが、知事はどう認識していますか。
○小池知事 東京都こども基本条例におきましては、全ての子供が誰一人取り残されることなく、将来への希望を持って、伸び伸びと健やかに育っていく環境を整備していかなければならないと規定されているものと認識いたしております。
都は、こども未来アクションを策定して、子供目線に立った政策展開をしております。
○福手委員 知事から大事な認識が答弁されました。
私の地元文京区では、女子学校の桜蔭学園に隣接するマンション、宝生ハイツの建て替え計画により、学校と周辺地域の環境が悪化すると市民が声を上げています。
パネルをご覧ください。これは以前、桜蔭学園のホームページに掲載されていたイメージ図です。今はもう掲載されていませんが、データを保存していた区民の方から提供していただきました。
この建て替え計画は、総合設計制度を活用して、一般の人が出入りできるスペース、公開空地を設ける代わりに規制緩和を受けて、このパネルにあるように、現在の地上八階建てから二十階建て、高さ七十メートル、容積率六〇〇%の高層マンションに建て替える計画となっています。
総合設計制度で建築するには都の許可が必要となります。許可され、高層建築が可能となれば、このパネルのように、教室にはほとんど日が当たらなくなります。接近してマンションが建てられることで、窓やバルコニー、公開空地から教室がのぞかれ盗撮されるおそれや、擁壁の上に立つ校舎への影響に懸念があります。
二〇二二年都議会第三回定例会では、桜蔭学園の理事長である校長と外一万四千七百十四人の署名の賛同によって、総合設計制度を使った建築計画の見直しを求める趣旨の請願が出され、付託された都市整備委員会と文教委員会のどちらも全会派一致で継続審査となりました。否決はされなかったということです。
地域では、地元町会や神社、学校が共同で会を立ち上げ、建築計画見直しの署名に取り組んでいます。署名はこれまでに二万筆を超え、今も増え続けているということです。
日照問題や公開空地の在り方など、意見をいっても取り合ってくれない、制度の中でやっているから地元の意見は認められないようで返事がないなど、憤りの声が上がっています。
伺いますが、総合設計制度の許可審査で許可されなかった事案というのはこの十年間でどれくらいあるのでしょうか。
○谷崎東京都技監 平成二十七年度から十年間において、申請を受け付けた後、許可しなかった案件はございません。
○福手委員 少なくともこの十年間は総合設計制度が許可されない場合はゼロなんです。許可制度といいながら、実態は許可しかない。制度として機能していないといわざるを得ません。
では、総合設計制度の許可が下りない場合というのはどういう場合ですか。
○谷崎東京都技監 建築基準法では、申請された建築計画が市街地環境の整備改善に資すると認められる場合は許可することができます。
都は、総合設計許可要綱にのっとり審査を行い、建築基準法に基づき、東京都建築審査会の同意を得て許可しております。
○福手委員 許可が下りない場合を質問しましたが、許可する場合を答えられました。
市街地環境の整備が改善されるものは許可するといいますが、この建て替え計画は、総合設計制度を活用することによって、日照阻害、プライバシー侵害、校舎損壊の危険など、隣接する学校にこれだけの被害を及ばせることになります。この計画をどう考えても市街地環境の整備改善とはいえないのではないでしょうか。
建築家で慶應大学准教授のホルヘ・アルマザン氏は、総合設計制度について失敗だったと話します。公開空地をビルの足元に設置することを条件に、床面積や建物の高さの制限を緩和することで、通常では不可能な大規模な超高層ビルの建築を許可している。しかし、公開空地は本来の公園や広場とは程遠く、厳重に監視された残余空間にすぎないと。そして、企業側による再開発を行政が後押しする政策だといっています。
東京都こども基本条例の中で、子供の意見表明権をちゃんと保障することは重要なことです。子供の声を聞くというのは、ただ聞くのではなく、大人の都合のいいことだけ聞けばいいのでもありません。子供のいいたい意見を保障することが重要なんです。大人にはそれに応える応答義務があります。そこも含めて、こども基本条例には位置づいているんです。
学校で学ぶ子供たちの声を聞きました。紹介をします。
日が当たり、明るい西館がとても気に入っているのに、ずっと日が差さなくなり、カーテンを閉めっ放しとなるのは悲しい。隣の住人と目が合わないように、すりガラスなどにされると、閉塞感を感じて鬱になりそうで不安です。のぞき見、盗撮の可能性、校舎崩壊の可能性があるのはとても怖いと思いました。どちらも取り返しのつかない結果を招く可能性があるものです。安心・安全な環境で学校生活を過ごすことを望むことはぜいたくなことでしょうか。子供、人の安全、命より優先されることはあるのでしょうか。大人は子供を守ってくれないのだろうか。不安です。どうか安心して、伸び伸びした学校生活を送らせてください。お願いします。
これ以外に声はまだたくさんありました。二十人近い子供たちの声、どれをとっても不安と心配の声ばかりだったんです。この声を聞いて、大人として何をすべきなのだろうと思わずにはいられないという声もありました。子供の声がこのように出されているのですから、これにちゃんと応える責任があります。
マンション建て替え計画が子供の権利を侵害することは子供たちの声が証明しています。子供の声も聞かないで、子供や学校に危険が及ぶ計画を進めるべきではありません。
東京都こども基本条例は、都議会の全会派が一致して制定された条例です。子供の声を聞くのは大事だと私たち都議会議員の共通認識となっています。
行政側も、各局が子供の声を聞く取組をやっていこうと、新年度も様々な計画を進めようとしています。それなのに、桜蔭学園の子供たちの声に向き合おうとしないで、この問題を放置してはいけないのではないでしょうか。
東京都はこの条例を守る責務があります。子供の権利を守る立場に立つのか、東京都の姿勢が大きく問われています。多くの都民がこの問題に注目しています。子供の最善の利益を守る結果となることを強く求めて、次のテーマに移ります。
3.補助犬の医療費補助について
補助犬について質問をします。
まず初めに、補助犬の重要性について、知事に認識を伺います。
○山口福祉局長 身体障害者補助犬は、身体障害者補助犬法に基づき訓練及び認定された犬であり、使用者の障害特性に応じて、視覚障害のある方がまち中を安全に歩けるように、一緒に移動などを行う盲導犬、肢体不自由のある方の日常生活動作を補助する介助犬、聴覚障害のある方に生活の中の必要な音を知らせ誘導する聴導犬の三種類がございます。
都は、身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、希望する障害当事者に身体障害者補助犬を給付しております。
○福手委員 私は重要性を聞いたんですが、答えがありませんでした。
自分に合った支援を選択できるということは大事なことです。私がお話を聞いた盲導犬ユーザーの障害者の方は、盲導犬を利用するメリットについてこのように話していました。
白杖で歩行するよりスムーズに、かつ安心して歩くことができます。白杖では一歩か二歩ぐらいの狭い範囲しか確かめられません。しかし、盲導犬の目を借りると、さらに広範囲の様子を把握でき、すぐ前を歩く人の歩調に合わせて歩き、大小様々な障害物を避け、まちの中を安全かつ迅速に移動することができるというふうに話されていました。
補助犬は障害者の方と一緒に生活をしています。その中で、病気やけがで病院に受診することがありますが、動物の医療費は十割負担で、障害者の方が負担をしています。
先ほど紹介した障害者の方は、医療費は補助犬の年齢や健康状態にもよりますが、健康診断に一万円、ワクチン接種で六千円から一万円、フィラリア予防薬三万円がかかり、そのほか適宜受診することがあるので、さらに医療費がかかると話されていました。さらに、大きな病気にかかり、手術や入院となると、一気に数十万円の支払いも予測され、経済的に不安になるとユーザーの障害者の方は話していました。
こうした補助犬ユーザーである身体障害者の生活の支援と補助犬の健康を守るため、東京都獣医師会は、予算と募金で補助犬の診療券事業を長年行ってきました。
しかし、私は昨年、東京都身体障害者団体連合会の方々から、補助犬診療券がなくなってしまったので復活してほしいと要望を受けました。東京都獣医師会が寄附により実施を続けるのが難しくなり、補助犬診療券は年三万円だったのを二万円に減額、そして、ついに停止になったんです。
東京都獣医師会、東京都身体障害者団体連合会から、補助犬診療券給付事業について、都の支援を求められたことはありますか。
○山口福祉局長 補助犬の診療に使用できる診療券を給付する取組は、公益社団法人東京都獣医師会が、募金活動による寄附金などを活用して、令和五年度まで行っていた活動でございます。
東京都身体障害者団体連合会からは、令和七年度予算に対する要望がございました。東京都獣医師会からは、当該団体が実施していた補助犬診察券給付事業に関する支援について、令和六年度予算に対する要望は出されておりましたが、令和七年度予算に対する要望は受けておりません。
○福手委員 東京都は毎年、各団体から予算に向けてのヒアリングを行っています。東京都獣医師会は、二〇二〇年度、二一年度、二二年度、二四年度の予算に向けて、知事のいる場で繰り返し要望を出しています。それを、今、一年分しかいわず、その一方で、来年度予算に対しては要望がなかったとわざわざいうのは、予算ヒアリングで出された要望を真剣に受け止める姿勢があるのかと疑問を抱かざるを得ません。
獣医師会の二二年度予算への要望書では、身体障害者の六割以上が年収百万円以下、三割が二百万円以下であることなどを示し、獣医師会の予算と募金だけでは支え切れなくなってきているとして、都の予算化を要望していました。しかし、それでも都は予算化しなかったために、今年度から診療券の給付が止まってしまったんです。
来年度予算に向けては、東京都身体障害者団体連合会から、獣医師会の補助がなくなり、治療費なども高額になっていることもあり、ぜひ都から補助をご検討いただきたいと要望がありました。
障害者団体からの要望であり、重いものです。障害者の社会参加と生活を支える重要な取組であるのにもかかわらず、しかも、物価高騰の下、とりわけ所得が少ない障害者の方の暮らしが大変なときに、補助犬診療費の負担軽減のための予算要望を断り続けてきた東京都には重大な責任があります。
東京都が補助犬の診療費の補助をしない根拠にしているのが、補助犬法第二十二条の規定です。二十二条は、補助犬を使用する身体障害者に対して、補助犬の体を清潔に保つとともに、予防接種や検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない旨の努力義務を規定しています。
しかし、共産党国会議員団を通じて厚生労働省に確認しましたが、補助犬法二十二条には財源の話は書いてなく、補助してはいけないとか、直ちにユーザーが負担しないといけないという規定ではない、自治体がユーザーの衛生管理その他に単独で補助することが禁止されていることは全くないということでした。現に、隣の埼玉県や横浜市は助成を行っています。
今、東京都では補助犬が百二十三頭、合計でいますが、例えば東京都獣医師会の要望書によると、補助犬に係る年間の獣医療費は一頭十万円です。補助額十万円で現在の頭数で計算すると千二百三十万円です。本来は都が予算化するべきものです。
そして、物価高騰の中で餌代の値上がりや、ユーザーからは医療費以外でも、リードやハーネスなどの消耗品には補助があってほしいという声もあります。補助犬の医療費等補助を予算化することを求めて、次のテーマに移ります。
4.特別養護老人ホームにおける水道料金負担について
最後に、特養ホームの水道料金について質問します。
特養ホームは人件費の次に重いのが水道代といわれています。水道代は、施設に入所する高齢者が食事をしたり、お風呂に入ったりして、家庭用として水を使い、生活する上で必ずかかる経費です。さらに、物価高騰も重なり、特養ホームの事業者から水道料金の負担が重いという声が上がっています。
では、特養ホームはどれくらい水道料金がかかっているのか聞いていきたいと思います。まとめて伺います。
まず、特養ホームで、口径四十ミリ、二か月で六百二十立方メートルを使用し、減免が適用されない場合は幾らか。また、同じ条件で、減免が適用されると幾らか。そして、同じ条件で、二十五人が入所する特養ホーム、つまり二十五世帯の共同住宅扱いが適用されると幾らになるのか、以上三点お願いします。
○西山水道局長 まず、メーターの口径四十ミリメートル、二か月で六百二十立方メートルの水量を使用した場合の水道料金を試算すると、約二十一万八千円となります。
次に、社会福祉施設減免を適用した場合の料金についてですが、社会福祉施設に対する減免は、昭和五十年の料金改定の際、都民生活に与える影響を緩和するため、議会の決議に基づき開始したものであり、その後も、料金改定やその時々の社会経済状況を考慮し、継続しております。この社会福祉施設減免を適用した場合の水道料金を試算いたしますと、約十九万六千円となります。
最後に、共同住宅扱いを適用した場合の料金についてでありますが、都の水道料金は、使用水量が増えると料金単価が上がる体系となっていることから、建物に一つのメーターしか設置されていない集合住宅では、各戸にメーターが設置されている住宅に比べ、料金が割高となる場合があります。
水道局では、こうした場合、料金負担の公平性の確保等を目的に料金算定の特例として共同住宅扱いを実施しており、集合住宅の屋内に水栓があることなど全ての条件に適合している施設に対し、申請に基づき適用しています。
当該施設が適用要件に合致するとすれば、試算額は約七万円となりますが、減免制度とは、その趣旨、目的が異なることから、単純に比較すべきものではございません。
○福手委員 共同住宅扱いが適用されると水道料金の負担が大幅に抑えられます。水道料金の負担軽減に非常に役立つ制度であることが分かります。でも、水道局のホームページで周知されているぐらいで、周知が十分とはいえません。
今回、共産党都議団として、都内九十の特養に実態調査を行いました。そこで分かったのは、七割近くの施設が共同住宅扱いを使っていない、四割以上の施設が共同住宅を知らないということでした。もっと周知を進めることを求めておきます。
特養ホームは入所する高齢者が生活をしているため、共同住宅扱いの対象施設となっていますが、住宅としてみなすことができないデイサービス事業所などが同じ施設の中にある場合は、水道メーターを別々に分けなければ共同住宅扱いにはなりません。
調査では、約六割の特養ホームがデイサービスと合築しており、そのうちの約七割の施設が特養ホームとデイサービスで水道メーターを別々にしていないと答えていました。メーターを分けていない理由としては、工事費がかかり難しいという意見が複数ありました。
知事、特養の水道料金の負担を軽減するため、制度をさらに改善するべきと思いますが、いかがですか。
○西山水道局長 共同住宅扱いは、居住実態を伴う建物において、メーターの設置状況により料金負担に差異が生じる場合があるため、公平性の観点から実施している特例でございます。
このため、居住実態を伴わず、制度の目的、対象に合致していない通所のサービスについては適用しておらず、特定の施設等を対象とした適用基準の見直しは考えてございません。
○福手委員 物価高騰の中、介護保険に関わる施設の閉鎖や撤退が増えています。これから高齢化がさらに進む中、よりよい制度へさらに見直すことを提案し、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)